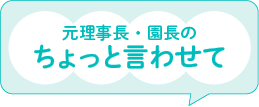年少さんの保育参観が終わった
2園の年少さんの保育参観が先週、終わった。
年中や年長がホールの大きなステージで劇や踊りを行う姿を、真剣な眼差しで見ていた年少さん。
そこから『自分もやってみたい』という自然な流れができる。
子どもは小さいほど、自分より大きい子の様子を見て『憧れ』を持ち、成長意欲が刺激され主体的にやってみようとする自分が作られる。
こんなことを教わったのは、もう何十年も前。
一つは故久保田浩先生の主催する「語る会」のメンバーに。
一つは筑波大学の教授(故杉原一昭先生、現名誉教授櫻井茂男先生)の開いて下さったゼミ。そこは現役の大学生や院生、そして現場の保育者が集まっての勉強会だった。
教育には理論があってそれに沿って行なうことの重要性を知った。
年少クラスの一角を仕切りステージに見立てているところはとてもアットホームだが、そこに立てた子どもの姿は、気の弱い私からすると『すごい!』と拍手だ!
「観てもらう事」、特に保護者参観の行事をする場合、4歳前後の子ども達にとってさえ何かしらのモチベーションが必要だと私は思っている。
でないと、やらせになるのでは、、、
あおば台では、保護者参観の日を含めても、劇をやる回数はせいぜい4回程度だ。
1回1回に子ども達に「みせてあげてもいいよ」という承諾をもらう、そんなやり取りがある。
参観日は、大好きなおうちの人に見せてあげる日だ。
いつもの幼稚園での姿が、おうちの人の前でどこまで出せるか、、そんなことがあおば台のこだわりだ。
『おうちの人が来てくれる!』という喜びが、幕が開き『あれ?お家の人以外にもいっぱいいる!』と変わるのは当然で、そこへのサポートに力を注ぐ。それが保育者の役割だ。
嬉しそうな顔、恥ずかしそうな顔、得意そうな顔。
しばらく自分の気持ちを調整するのに時間をかけながら、子ども達は劇での役割を果たそうとする。
あんなに小さくて、見ようによってははかない存在。
そんな子ども達が、おうちの人のために一生懸命に行う。
心が洗われる。
幼稚園も、その絆を作られたお父さんお母さんと一緒のたくさんの手で、慈しんで育てていけたらと思っています。