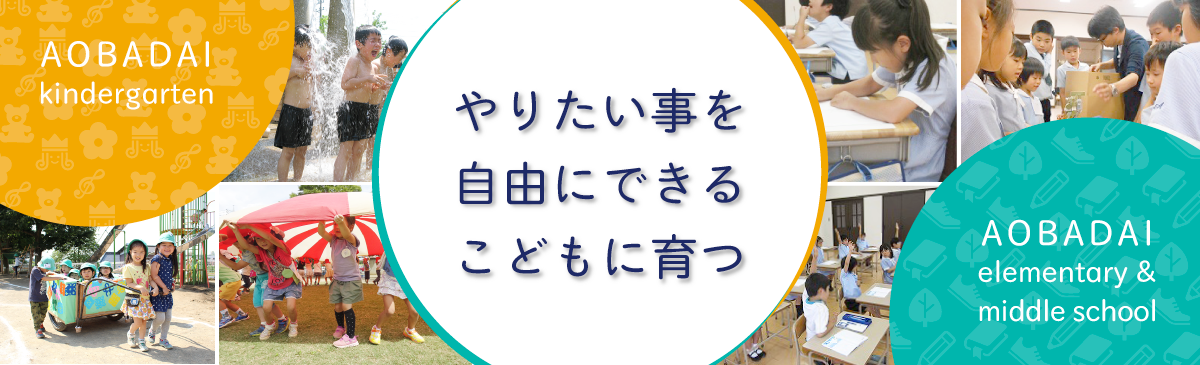理事長・園長のちょっと言わせて
しばらく見なかった風景
家の庭にあるもみじがいつの間にか散ってしまっている。何日か前は真っ赤に燃えるような色をつけていたのに、もっとゆっくり見ておくべきだった。家の裏にある大きな土山に、山の下につながれているヤギがその山の中腹まで登って行って草を食べている。ヤギは何を考えているのか、いつも食べることだけしか考えていないのか、土山を登るときは、こちら側がよいとかこちらは危険だとかの考えはないのだろうか。それでも幸せなのだろうか。いやそのような意識は持てないのだろう。そのような意識が持てないほうが幸せなのか、それとも意識をはっきりと持てる人間のほうか幸せなのか。
あおば台幼稚園の周りの風景も少しずつ変わっていっている。南の道を挟んだ近くには住宅が建っているし、今日はその一角で住宅展示会か見学会をやっている。東側正面玄関の前は、少し前まで田んぼであったけれど、そこを埋め立てて空手道場が建った。これからは、道場に通う彼らが、幼稚園の警備を担当してくれるだろう。工事に来ている職人さんが自分たちが施工した側溝のところに座って、みんなでタバコをふかしている。ずいぶんとうまそうに煙を吸い込んでは吐き出している。物を作り上げるという自負心が、年老いた親父たちの顔ににじみ出ていて、力強い頼もしさを感じる。
私ももっともっと若かった時に同じような土方仕事をしていた経験がある。一日の日当が1600円だった。腕の良い職人さんは3000円。親方格になると3500円だった。日当が少なくても、それがどのような意味かをよく理解していたから不満など全くなかった。給料をもらって、ガソリン代を払うとあまり手もとに残らない。それでも意気揚々としていて、朝方まで飲み歩き、あくる日はしゃきっとして仕事へ出て行ったものだった。今のように土曜日曜が休みだなどと言われると、食えなくなってしまって日干しになってしまう。それでもなんだか、毎日が幸せだったような気がする。
あの時のことを思うと、今のほうが経済的には楽にはなった。いや、私の資産の話をすると結婚前より全く乏しくなって、話せるようなものではないが、生活そのものは文明とともに楽になっている。仕事にも恵まれ、子どもとともにいられる仕事は最高に素晴らしい仕事である。しかも運もよく小学校まで作らせて頂いた。何も不満はない、何か不満でもあるのかと自分自身を問い詰めてみると、都合のよいことを言ってのらりくらりと逃げてしまう。子どもと一緒にいられることは何事にも代えがたいことだが、それ以外はだれかにやってもらってもいいなんて、情けなくも逃げ出そうとする自分がいる。
今日は仲間の認定子ども園の認可になった建物の竣工式で、招待されて挨拶をしてきた。早稲田の応援団にいた凄い先輩だけど、彼も大変な時があったのだと思うと少し重荷が取れたような気にもなった。私も人生つきまくっているようだけれども、彼もつきまくっている。本人がそう言っていたから間違いないだろう。
16:45 | 投票する | 投票数(11)
2014/12/12
アベノミクス
| by:塚原 港
安倍首相の唱えた経済政策で三本の矢にたとえられているものだ。デフレが進行し景気を何とか回復させるべく、日銀と協力して円安に持って行ったけれど、その間に消費税率を今までの5%から8%に上げたためにまた景気が落ち込んだ。消費税を上げないと、掲げた政策がうまく行かないこともあって、政策遂行のために円高是正をしたようなものだが、意外とうまくいかないものだ。野党が政権を取ったところで自民党よりうまくいくことはない。もっと混乱を招くだけだ。この際、圧勝して安倍さんには腰を据えて経済政策に取り組んでほしい。
円安で史上空前の莫大な利益を得た大手の自動車会社などは、為替で得た利益は為替で損もするという理屈で、その利益を下請けに回そうとしない。お金が大会社でだぶついているだけでなかなか下請まで下りて来ないのも、景気が停滞している所以でもある。大会社ばかりが潤っていて、中小企業までお金が巡回して来ないのだから、零細企業などはおこぼれもない。私たちの事業所などは経常費補助金が頼りで、まったくの他力本願であるので力の出しようがない。景気のよくなったという実感がないどころか、みんなは物価が高くなったから、実質給与が目減りしていると言っている。
以前の消費税から5%上がるわけだから、5%以上の給与を上げなければみんなの暮らしは良くならないではないか。まず所得が上がってから消費税をやったら良かったのではないか。まず塊より始めよで、公務員から給与を上げていくのはいかがなものだろうか。経常費は今年度はすでに決定していてこれから増額されるということもないから、昇給はどうしたら良いのか。私たちの仕事はブラック企業になってしまうではないか。新採の初任給をどうするかではなく、今いる教師の次年度の昇給について思い切ったことをしなければ、いつまでも彼らの犠牲に頼ってはいられないだろう。
私立学校の教師は公務員の教師と所得を比べられる。教育内容は私立独自のものがあるから、断然私立の方が選択余地があると思うけれども、学校教員になりたいというより公務員になりたいという人の方が多い。また私立の幼稚園教諭は公立の学校教員から比べると、情けないほど低給である。学校教員も仕事は良くするけれども、幼稚園教諭はそれと比べて優るとも決して劣ることはない。しかも私立の学校というのは、常に競争の中に晒されていて自己研さんを怠るとすぐにお払い箱になる。なのに公立より給与が低いのは納得がいかない。いつの日か、学校教諭も幼稚園教諭も同格の給与になることを夢見ている。
今日の餅つきはあおば台で行われた。仕事を休んでお手伝いに来てくれたお父様ありがとうございます。昨日からもち米を冷やしておいてくれたりして、またおいしいけんちん汁を作ってくれたお母様ありがとうございます。おかげで子どもたちは大喜びです。心から感謝いたします。
アベノミクス
安倍首相の唱えた経済政策で三本の矢にたとえられているものだ。デフレが進行し景気を何とか回復させるべく、日銀と協力して円安に持って行ったけれど、その間に消費税率を今までの5%から8%に上げたためにまた景気が落ち込んだ。消費税を上げないと、掲げた政策がうまく行かないこともあって、政策遂行のために円高是正をしたようなものだが、意外とうまくいかないものだ。野党が政権を取ったところで自民党よりうまくいくことはない。もっと混乱を招くだけだ。この際、圧勝して安倍さんには腰を据えて経済政策に取り組んでほしい。
円安で史上空前の莫大な利益を得た大手の自動車会社などは、為替で得た利益は為替で損もするという理屈で、その利益を下請けに回そうとしない。お金が大会社でだぶついているだけでなかなか下請まで下りて来ないのも、景気が停滞している所以でもある。大会社ばかりが潤っていて、中小企業までお金が巡回して来ないのだから、零細企業などはおこぼれもない。私たちの事業所などは経常費補助金が頼りで、まったくの他力本願であるので力の出しようがない。景気のよくなったという実感がないどころか、みんなは物価が高くなったから、実質給与が目減りしていると言っている。
以前の消費税から5%上がるわけだから、5%以上の給与を上げなければみんなの暮らしは良くならないではないか。まず所得が上がってから消費税をやったら良かったのではないか。まず塊より始めよで、公務員から給与を上げていくのはいかがなものだろうか。経常費は今年度はすでに決定していてこれから増額されるということもないから、昇給はどうしたら良いのか。私たちの仕事はブラック企業になってしまうではないか。新採の初任給をどうするかではなく、今いる教師の次年度の昇給について思い切ったことをしなければ、いつまでも彼らの犠牲に頼ってはいられないだろう。
私立学校の教師は公務員の教師と所得を比べられる。教育内容は私立独自のものがあるから、断然私立の方が選択余地があると思うけれども、学校教員になりたいというより公務員になりたいという人の方が多い。また私立の幼稚園教諭は公立の学校教員から比べると、情けないほど低給である。学校教員も仕事は良くするけれども、幼稚園教諭はそれと比べて優るとも決して劣ることはない。しかも私立の学校というのは、常に競争の中に晒されていて自己研さんを怠るとすぐにお払い箱になる。なのに公立より給与が低いのは納得がいかない。いつの日か、学校教諭も幼稚園教諭も同格の給与になることを夢見ている。
今日の餅つきはあおば台で行われた。仕事を休んでお手伝いに来てくれたお父様ありがとうございます。昨日からもち米を冷やしておいてくれたりして、またおいしいけんちん汁を作ってくれたお母様ありがとうございます。おかげで子どもたちは大喜びです。心から感謝いたします。
海外語学研修の経過
月曜日にグアムのセントジョンスクールへ向かった子どもたちの様子を、現地からK先生が報告してくれた。K先生の感想が私と同じような感覚であったのがうれしかった。私も現地報告とまではいかないけれども、帰ってきてから感想をこの欄に書かせてもらった。K先生の現地での報告を読んで、その時の自分の気持ちがよみがえってきた。あのような教育の主体では、それが正しいやり方だろうなと思っても、日本では受け入れられないだろうと残念に思う。
しかし私は残念に思うだけではとどまらないのが私の性格だから、必要だと感じたことは、特に3年生以上の子どもたちにはそれを試したりもする。それに偉人伝を読みその感想を書いて来るなどと言うのは、子どもたちの目標の支えを作るのにとても大切なことだと思っている。それが科学者とかだと、理科だの算数だのと教科に結び付けて考えてしまうのが日本の教育にいやらしいところである。そんなことよりその子の人生において大きなインパクトになればすごいことではないのかと思うけれども、教科にして作文の評価を考えてしまうのには悲しい。
アメリカの授業がすべて良いとは思わないけれども、自分がどう考えるのかと言う問題が多いことは確かだ。論文形式が多いのでそれに論評を加えるのにはそれだけの知識と哲学を持たないと、子どもたちを説得できない。まあどこの国でも立派な教師ばかりがいるとは限らないだろうけれども、できれば子どもの気持ちのわかる教師の集団にしたいものだ。勉強はどうするのだといつものようにたずねてくる人もいるだろうけれども、学習というのは子ども自身が内発的動機づけに従って机に向かうものだ。
幼稚園ではリヤカーの試験が終わった。子どもたちには生まれて初めての試験で、リヤカーの免許証いなんて世界にあおば台にしかない。年長を持つご家庭では、子どもたちがどのようなことをお話していたのか、記憶に止まっていることがあったら連絡長でお願いしたいと思います。車の免許と同じように、クランク、S型、横断歩道、車庫入れと大変難しいのがあります。自分の歩いている位置とリヤカーのタイヤの位置が理解できないと脱線してしまいます。今日の私は厳しい試験官であります。
もっとレアな話
1・2年生はつくばローズガーデンへ行った。イギリスやフランス生まれの種類のバラもあり、300種2500本のバラが植えられている。かつてはつくば市の市長をなさっていた藤澤さんも、今ではローズ爺と呼ばれているそうな。上の左側の写真はローズ爺から説明を受けている子どもたち。右側和ガーデン中央で集合写真。
ファミリアに別れて自分たちが気に入ったところで写生をしたり観察している様子であるが、バラに囲まれて気分がいいだろうなと思う。とても挨拶がよく、『この辺の子ではないね』などと来ている大人に言われていたけれども、子どもたちが私の顔を見て『校長先生!』なんて大きな声で呼ぶものだから、『この辺の子なの?』と周りの大人たちは方向転換してしまった。それはどうゆうこと?。
幼稚園の子どもたちが食事をしようとしているところ。4年前は初等学部の子どもたちが次々と熱中症で倒れてしまって、このローズガーデンに救急車が何台も来たことがあった。
同じように来ていたあおば台幼稚園の子は誰一人として倒れる者はいなかった。
逞しいあおば台幼稚園の子どもたち。幼稚園の時にペアだったお兄ちゃんが初等学部にいて挨拶に行ったりしていたけれど、小学生のお兄ちゃんは『悪いけど忙しいから』と恥ずかしそうにしていた。
ちょっと寒い日で雨
今日は雨で昨日のように半袖でいると肌寒い。けれども半袖のまま外に出て、雨の中を楽しんでいる子どもたちがいる。いつでも子どもたちは普通でないことをしたがる。それが子どもの特権なんだろう。だからそういったことを理解している大人は、そのような子どもの姿を微笑ましく見ている。そして子どもは大きくなっていくのだ。大人たちも実はそのように育てられていたはずである。多くの大人たちから寛容に許されながら育てられた。でも忘れてしまった。
雨に濡れて寒くなれば、濡れた物を乾いたものに取り替えたくなる。それを要領良くやれるのが小学生だ。どんなに濡れていても立ったまま動かないのが幼稚園の子たち。だから保育者はどんな天候の日でも四方八方に気を配り、広角レンズのように目を光らしていなければならない。初等学部の今日の保健室は、めまぐるしく児童の往来が激しかった。そこで親がいれば、親が何かと口を出して手を出すだろうが、いないということが幸いして、自分の力で何とかしなければならない。
子どもはみんな素直な子に育てたい。素直というのは、ただ大人に迎合し、服従を誓い従順に育てるということではない。それではロボットか奴隷であって人間として育たない。私の言う素直と言うことは、事にあたって損得を考えずに精いっぱいの力を発揮することだ。だから家庭教育の中で、損得の話を多く持ちだすと、素直な子は育ちにくいことになる。その上で男子は荒々しく勇気のある子に、女子は頭がよくて思いやりのある子に育てたい。
私は発達のプロで、それなりにアクションプランも立てることができるし、何人かの6年生を卒業させてきた。たまたま素直な子どもたちだったので運が良かったこともあるけれども、卒業した子どもたちはみんな素晴らしい。彼らは根が真面目であるということもあるけれども、きっと幸せになれるだろう。素晴らしい子を育てるために、絶対にしてはならないことがある。『お前はだめな子だ』『何故これが解らないのだ』というやっつける否定語である。
子どもの前で他を批判することも素直な人間を作るのには邪魔で、却って非社会的な子を作ることになる。大人の考える社会正義と子ども社会での社会正義は違う場合もあるから、自分が正しいと思っていることだけを押しつけるのは間違っている。なぜなら子どもは親の前で反論できないから、そのまま子どもが親の意見をコピーしてしまうと子ども社会で異端児になってしまう恐れがある。拘りを持たずに(刷り込みをせずに)意見を聞くべきであろう。
親は親としてプロだが、それがそのまま子育てのプロであるとは限らないので、プロの意見を取り入れるようにお勧めする。しかし断っておくけれども、子どもは最後には親元に帰さなければならないので、子どもへの責任は親が取るべし。しかし私たちもまた『子供への責任』から逃れることはできないことは当然のことだと理解している。